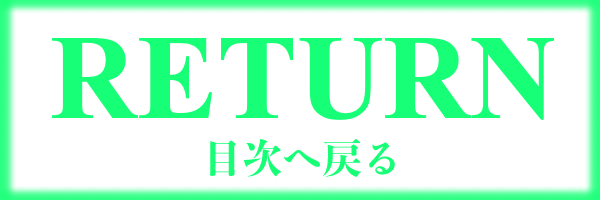アンジェリカ・ミルフーヴァ〜師への恩と愛〜
数時間後。
音楽教室の入口の鍵が解除され、ドアが開いた。
「フォルデ先生、アンジェです」
なにも状況を知らないアンジェリカが、いつもの調子でゆっくりと入室した。
だが、部屋の照明がほとんど点いていない上、肝心のフォルデの返事がなかったことに違和感を抱いたようだ。
「…先生? いらっしゃいますか?」
「ここにいるぞ」
暗がりから俺が声を上げる。目的の人物と異なる声に、アンジェリカは驚いた様子だ。
「ど、どなたですか…?」
「この状況でも丁寧な口調を崩さないのはさすがだな。アンジェリカ・ミルフーヴァ」
俺は部屋の照明を一部点けた。灯りの下に映し出されたものに、アンジェリカは息を呑んだ。
「! 先生!?」
フォルデは椅子に縛り付けてある。頭を覆っていた袋は取り去る代わりに、目にはアイマスクを装着し、口には布切れを詰めた上で粘着テープを貼っておいた。
アンジェリカは即座に彼の元へ駆け寄ろうとする。だがそれよりも俺が銃を突きつける方が早い。
「おっと、その場から動かないでもらおうか。従わないとどうなるか…わかるよな?」
「…!」
チャキ、とわざとらしく音を立ててアピールする。アンジェリカはフォルデに差し伸ばした手をゆっくりと下ろし、その場に止まった。
「せ、先生になにをしたんですか…!?」
「安心しろ。少し眠ってもらっているだけだ。俺が用があるのは、お前の方だからな」
「私…?」
「言うことを聞けば、こいつにはこれ以上なにもしない。用が済んだらすぐにでも解放してやる。だが従わなかったり、妙な動きを見せれば…」
俺は銃口をグリグリとフォルデの頬に押し付け、もう片方の手でフォルデの小指を握った。
「二度とバイオリンを弾けない身体にしてやるのは一瞬だ。やり方はいくらでもあるからな」
「っ! やめてください!」
抵抗すれば俺がどうするのか察したのだろう。アンジェリカが声を荒げて訴えた。
「なんでもしますから、先生にこれ以上手を出さないでください!」
「くくく…素直で助かるよ」
名家の令嬢からすれば、たかが習い事の教師など見捨てれば良いものだ。それだけミルフーヴァ家の血筋であることの価値は大きい。
「まあ、ご令嬢が我が身可愛さに一般市民を見捨てたとなれば、世間からの批判は免れないだろうしな?」
「そんなことは関係ありません…! 先生は私にとって大事な方、ただそれだけです…!」
そうだろう。この数日のフォルデとのやり取りを見れば、もうこの二人はただの講師と生徒の関係ではなくなっていた。
だからこそ、それが命取りになるわけだが。
「なら、ここからは行動でその想いを示してもらおうか。パーソナルデバイスの電源を切れ」
「…!」
アンジェリカは目を見開き、後ずさった。パーソナルデバイスはGPS機能や緊急通信機能も搭載された自己防衛の要。この状況で機能をオフにすることの恐ろしさは明らかだろう。
「どうした? こいつがどうなってもいいのか?」
「っ! ま、待ってください、従います…!」
アンジェリカは首元に手をかざした。すると彼女の目の前にいくつかのホログラムが浮かぶ。パーソナルデバイスの設定画面だ。
「余計な操作はせず、電源を切ることだけしろ。こっちから見てもわかるからな」
「は、はい…」
アンジェリカは手を震わせながらも操作を続けた。
やがてホログラムの中にシャットダウンの表示が見え、彼女のパーソナルデバイスはその機能を停止したことを確認した。
「よし、次だ。これを咥えろ」
「こ、これは…」
俺がアンジェリカの足元に投げ渡したのは、黒いゴム製のマスクだった。口に当たる部分には穴付きのボールが付いており、装着するにはこれを口に咥えなくてはならない。
見慣れないものだっただろうが、その形状を見て装着するとどうなるか理解した様子だ。
「二度は同じことを言わんぞ。さっさとしろ」
「! は、はい…」
彼女は観念し、マスクを手に取って口元にボールを当てがった。
咥える前に動きを止め、俺の方を見て言った。
「あ、あの…!」
「なんだ? 勘弁してくれなんて要望は聞かんぞ」
「いえ! 先生には…どうかなにもしないでください! お願いします…!」
「お前がきちんと言うことを聞けば、ちゃんと解放してやる」
「………」
アンジェリカは不安げな表情でフォルデを見つめ、今度こそボールを口に咥えた。
「は…がっ、あぁ…!」
上品なお嬢様のことだ。大口を開けてなにかを咥えることなどそうそうにあるまい。
涙目でえづきながらも、彼女は口いっぱいにボールギャグを咥えた。
黒い生地が鼻から顎にかけてぴっちりフィットし、彼女の表情を覆い隠した。
「マスクのベルトをきちんと締めろ」
「おぉ…」
アンジェリカがマスクの左右のベルトを後頭部で接続すると、自動的にロックがかかった。ピピッと音が鳴り、彼女の顔を締め付ける。
これで彼女は言葉の自由を奪われ、助けを呼ぶこともできなくなった。
「む、うぅ…!」
「くく、よく似合っているぞ。次はこいつを足に嵌めろ」
俺が投げ渡したのは、2つの金属製の輪が肩幅程度のワイヤーで繋がった足枷だ。
アンジェリカはもう抵抗の意思を示すことなく、おずおずとリングを両足首に嵌めた。
リングを閉じてロックがかかると、ワイヤーが赤く発光した。
足を肩幅までしか開くことができず、脱走も抵抗も難しくなる。
「ここからは俺が仕上げてやろう。両手を背中で組め」
「っ…!」
俺が近づいてきて後退りするアンジェリカ。それ以上逃げられるより早く、俺は彼女の身体を抱き寄せた。
「その状態で今さら逃げられると思っているのか? さっさとしろ」
「うぅ、ぐすっ…」
泣きながら両腕を後ろで組むアンジェリカ。その両手首に手錠をかけると、もう彼女は一切の抵抗の手段を封じられた。
俺はもう一つの機械を取り出すと、彼女の首をホールドした。
「んんっ!?」
「じっとしていろ」
ドライバーの先端のような形状の端子を、彼女のパーソナルデバイスに挿し込んだ。
電源はオフにしてあったが、アンジェリカのパーソナルデバイスの設定画面がホログラムとなって表示される。
俺はその設定のいくつかを弄った。
「んんーーーっ!!」
やめてと言わんばかりにアンジェリカがくぐもった悲鳴をあげた。なにをされているのかわかったからだ。
サキの時と同様に、パーソナルデバイスの緊急通信機能、GPS機能など、防犯に関わるものをすべて無効にした。
サキが意識を失っている間にされたのとは対照的に、こっちは目の前ではっきり見える中設定を変更した。
その絶望感たるや、想像に難くないだろう。
「さあ、これで準備は整った」
俺はそのままアンジェリカをお姫様抱っこの形で持ち上げた。
「んんっ!?」
どこに運ばれるのかわからない恐怖で、彼女は呻き声を上げる。だが手足の自由はすでに奪われ、逃げ出す手段はない。
フォルデを拘束した後、俺はこの部屋にターゲット運搬用のコンテナを運び込んでおいた。
薄暗い部屋の奥で、コンテナは中身が入るのを口を開けて待ち構えている。
「しばらくこの中で大人しくしていてもらおうか」
「んんっ!!」
首を振って嫌がるアンジェリカ。コンテナに収納される直前、フォルデの姿が視界に入った。
「ふぇんふぇい…!」
これが最後に見る先生の姿となるだろう。もっとも、その表情は目隠しとテープで覆われてしまっているが。
「ふ、ふぐっ、うぅ…!」
幸せな逢瀬は1週間近くで終わった。まさかいつも通りにレッスンに来たら今生の別れを経験する羽目になるとは夢にも思わなかっただろう。
「くくく…別れはつらいか? 安心しろ。拠点に着いたら、あんな男のことなど考えられなくなるようにしてやるからな」
「んんんーーーっ!!!」
涙を流し悲鳴をあげるアンジェリカの顔を見ながら、俺はコンテナの蓋を閉めた。
あとはサキの時と同様に、これをバレないようにコロニーの外へ運び出すだけだ。
音楽教室に俺が侵入した痕跡がなるべく残らないように確認しつつ、フォルデに声をかけた。
「それじゃあな、フォルデ先生。お前が見込んだ生徒は俺がしっかり教育してやる。次に逸材を見つけたときは、せいぜい奪われないように気をつけることだ」
眠っている彼にその言葉が伝わったかはわからない。
俺はコンテナをビルの外へ運び出すと、近くに止めておいた車に載せて繁華街を後にした。
コロニー外壁の検問は今回もクリア。その後は障害もトラブルもなく宇宙船に帰還することに成功したのだった。