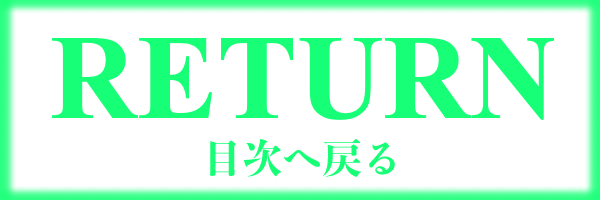サキ・イチミヤ〜彼氏のプライド〜
路上キス映像だけでは、サキを大人しく同行させる脅迫のネタとしては弱いだろう。
例えばこれを見せて「バラされたくなかったらついてこい」といったとして、サキが開き直りでもしたら一巻の終わりだ。
サキは直接関わっていないけれど、彼女にとって大切な人や物のために、言うことを聞かざるを得ない。そんなネタが見つかれば拉致計画の成功率は大きく高まる。
それが見つからなければ、リスク承知で無理矢理攫うしかなくなる。できればそれは最終手段にしたいところだ。
というわけで、今日はケビンの方に何かないか嗅ぎ回っている。
放課後のサッカーグラウンドを再び訪れると、いつも通り男子たちはボールを追って駆け回り、サキはその動きを観察していた。
この日は試合形式の練習で、部員を2チームに分けて戦っていた。みんな真剣度が増した表情で、ケビンの動きもこの間見たとき以上にキレとスピードがあった。
練習試合はケビンが属するレギュラーチームが3-1で勝利し、終わった後は顧問やサキを交えてミーティングが行われ、解散となった。片付けが終わっても特にこれといったトラブルは発生せず、普通の部活風景を見ただけだった。
「無駄骨だったか…」
これ以上張り込んでいても収穫はなさそうだと思い、帰路に着こうとしたときだった。
ケビンが部員を3人引きつれるようにして、校舎に向かっていった。
「…?」
彼らの表情を見るに、ただ事ではない様子。
しかも校舎の中には入らず、建物の裏の人目につきにくい場所へ歩いていた。
「あの場所ならいけそうだな」
アカデミーが特にセキュリティに力を入れているのは、校舎内への出入口だ。建物の裏側なら、警備員やドローンに目をつけられない限り自由に行動できる。
俺はケビンたちの様子を窺うべく、校舎裏に回り込んだ。
校舎裏には木々が立ち並んだり、倉庫用のコンテナがあって身を隠しやすかった。
物陰からのぞくと、ケビンが部員に対して何か言っていた。俺はファミレスで使用した盗聴ドローンを起動し、彼らの近くまで移動させる。
音声はすぐに聞こえてきた。
「なんであそこでお前が俺より前に出てきてるんだよ! あの位置からシュートできたのに、射線を遮るなよ!」
「いや、作戦じゃあのラインまではパスしながら進むって話だったじゃないすか…」
「あの位置から打っても、ディフェンスに取られる可能性が高いっすよ」
ケビンの前に立たされている3人は見覚えがある。全員レギュラーチームで、学年はケビンより下だったはずだ。
どうやらケビンは先ほどの練習試合での動きに不満があるらしい。ミーティングではそのような話に発展していなかったはずだが、こうして校舎裏に呼び出したということは、全体では言いにくい内容だったのだろう。
「つーか、なにがそんなに不満なんすか? 試合は勝ったし、動きも練習通りにできてるのに」
「俺たちは得点を決めなきゃいけないポジションじゃないんすよ?」
「だからって、ずっと得点アシストする動きばっかでいいわけないだろ!」
「それは状況次第だし、俺たちが勝手に決めて動いていいことじゃ…あ」
後輩の一人が、なにかに気づいたようにニヤけた。
「もしかして先輩、サキちゃんにかっこいいところ見せたかったんすか?」
「ああ!?」
「やっぱあの噂って本当なんすか? 先輩がサキちゃんと…」
後輩の言葉は、それ以上続かなかった。
ケビンの拳が顔面を捉え、後輩は背後の壁に叩きつけられた。
「ってぇ…!」
「お、おい! 大丈夫か!?」
「ちょっと先輩、落ち着いてくださいよ!」
ケビンの顔は怒りで真っ赤に染まっていた。
「なにしやがんだよ…!」
殴られた後輩は、もう敬語を使う気もなかった。
「お前ら、サキのことも含めて余計なこというんじゃねえぞ! 試合に出れねえような身体にされたくなかったなぁ!」
ケビンは一方的にそう告げると、後輩たちには目もくれずその場から立ち去っていった。残された3人は口々にケビンへの悪態をつき、殴られた部員を労わりながら一緒に引き上げていった。
その場に誰もいなくなるまで、俺は笑い声が漏れそうなのを必死に堪えていた。
こんな幸運があるだろうか。
向こうから簡単にボロを出してくれた。
「今どき、こんなパワハラがあるんだな…」
戻ってきたドローンの音声を確認すると、先ほどの騒動が殴る音も含めてきちんと録音されていた。もちろん場の不穏な空気を感じ取った瞬間から、カメラも回して映像に収めていた。
ケビンが後輩を殴る瞬間は、バッチリ記録されている。
アカデミーサッカー協会にでも知れたら、この部は終わりだ。
「これでサキを脅すネタは十分揃ったな」
・ケビンは後輩を呼び出し、一方的に殴った
・ケビンのパワハラは映像と音声共に記録されている
今日の出来事については、サキは当事者ではない。
だが付き合っている彼氏が部内暴力を働いたとなれば、当然無関係ではいられない。この関係性を利用させてもらうとしよう。
「いよいよ最後の詰めを考えるところにきたな…」
初めての拉致実行の時が、刻々と近づいてくるのを感じて胸が高鳴ってきた。
絶対に成功する保証などなく、失敗すれば俺はすべてを失うだろう。
だがその不安以上に、成功した先に待つ楽しさにワクワクしていた。
成功する確率をより高めるため、俺はどのようにしてサキにアプローチを仕掛けるか頭の中でシミュレーションを繰り返すのだった。
「待ってろよ、サキ。もうすぐお前を迎えに行くからな…」