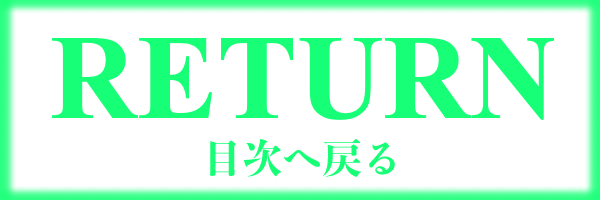サキ・イチミヤ〜偽りの交渉〜
数日後、ついにその時が訪れた。
いくら付き合っているとはいえ、ケビンとサキはいつも一緒に下校できるわけではない。
この日、サキは一人で校舎から出てきた。
クラスメイトと別れの挨拶を交わし、寄り道せずに商業地区を抜けて住宅街へ。
人気が少なく、監視ドローンの死角になるポイントはこの数日ですでに割り出していた。
サキがそこへ通りがかったところで、俺は彼女に接近した。
「ちょっといいかい? C9アカデミーの学生さんだよね?」
「え、はい」
急に声をかけられ、サキは警戒しながらも応えてくれた。応答してくれさえすれば、あとはこっちのものだ。
「急にごめんね、俺はこういう者なんだけど…」
「! サッカー協会の…」
俺がホログラムで表示した身分証は、アカデミーサッカー協会の関係者を示していた。もちろん本当に所属しているわけではなく、偽造したものだ。
だが、本当に協会の人間かどうかなどその場でいちいち確認する学生なんていない。サキはとりあえずその話を信じ、話に乗ってくれた。
「君はサッカー部の関係者…多分、マネージャーさんか何かだったよね?」
「はい、そうですが…あの、何か?」
「ちょっとこれを見てほしくてね」
そう言って俺は、映像を再生した。それは先日盗撮した、ケビンの後輩に対する暴力映像だった。
最初は怪訝そうに見ていたサキの表情が、次第に青ざめていった。
「うそ、先輩…!?」
「実は昨日、協会に相談があってね。名前は出せないんだけど、C9アカデミーの人間がこの映像を撮影してたんだ」
サッカー協会に限らずほとんどのスポーツ協会には、指導やチーム強化にかこつけて非人道的な行い、ハラスメントが常態化しないように相談できる窓口が設けられている。
この相談目的で盗撮、盗聴することは法的に罰せられることはなく、相談した人間の情報も保護される。
俺が今演じているのは、その相談窓口の担当者というわけだ。
「相談を受けて、殴られた生徒に事実関係を確認したら、これは捏造じゃなくて本当に殴られたと言ってたよ」
「そんな…」
「その子は殴った生徒…ケビン・シュナイダーくんを訴えるつもりらしい。協会としても部内暴力の疑いがある以上、見過ごすわけにはいかないんだ」
「まさか…大会への出場停止、ですか…?」
サキが口元を手で押さえ、涙目で訊いてくる。
「このままだとそうなるだろうね。だけど…」
俺はすかさず続けた。
「俺はまだ、このことを上に報告していない」
「え、どうして…?」
「君たちくらいの年齢の子なんて、頭に血が上ってつい…なんて間違いを起こすことはザラにあるだろう? ほんの一瞬の過ちで学生のチャンスが奪われるのは、俺だって心が痛い」
自分でも内心吐き気がするような綺麗事を言っている。
だが、サキは俺の話に完全に耳を傾けてくれている。
「だから、君に力を貸して欲しいんだ」
「私が…?」
「部員から聞いたんだけど、君はケビンくんと親しいそうだね? 君が間を取り持てば、ケビンくんは謝罪し、殴られた子も考え直してくれるかもしれない」
「…!」
「もちろん結果は当事者同士の気持ちの問題になるけど…どうだい?」
「…やります! 私からケビン先輩に話をしてみます!」
サキは決意のこもった目で応えた。
本当にこの娘は純真で、いい子なのだろう。
心の中で醜悪な笑みを浮かべながら、俺は穏やかな表情で頷いた。
「わかった。それじゃあケビンくんに話をする前に、被害にあった部員の説得にも協力してもらっていいかな? まずは彼に落ち着いてもらわないと、話が進まないからね」
「そ、そうですね…! じゃあ、その人に連絡を…」
「あ、待って」
おそらく連絡先を交換しているのだろう。殴られた部員と連絡を取ろうとするサキを制止した。
「実は向こうにその子を待たせているんだ。ついてきて欲しい」
「え?」
「すぐそこの公園のところだよ。彼にも待ってもらうように話を通してあるから、わざわざ連絡を取らなくても大丈夫」
「そうなんですか…? わかりました」
歩き出す俺の後を、サキがついてきてくれた。ここで彼女がついてきてくれるかは賭けだったが、勝利したようだ。
おそらく、普段のサキだったらもっと警戒していたかもしれない。そもそも、本当に俺がサッカー協会の人間なのか、殴られた生徒が本当に訴えようとしているのか、疑って確認する余地は十分にあった。
だが自分が打ち込んでいるサッカー部の活動停止、付き合っているケビンがその騒動の発端となっているという焦りが、彼女の思考と判断を鈍らせたのだろう。
移動する道中、民家からもドローンからも死角になるポイントがあった。そこに車を停めてある。
「この中で話そう」
「え、あの…本当に彼はここに…?」
どうやら歩いているうちに、少しずつ思考が冷静になって違和感を覚えたらしい。
だが。
「くくく…もう遅い!」
「っ!?」
ここまで連れてくれば、こっちのものだった。
俺は振り向きざまに、隠し持っていたスプレーの吸入器をサキの鼻と口にあてがい、スプレーのノズルを押した。
プシュゥゥウウ!!
「うっ!? な、なに、を…」
不意をつかれたサキは、中身の催眠ガスを吸ってしまった。
即効性の高いこのガスの効果はテキメンで、瞬く間に彼女の目はトロンとなり、足取りがおぼつかなくなる。
俺は倒れそうな彼女を抱き寄せ、車の後部座席に放り込んだ。席は取り外してあるので人が数名横になれるほどのスペースがある。
「ぁ…だれ、か…たす、け…」
悲鳴をあげて助けを求めようとしたが、もう声を出す力も入らないようだ。
俺はそこでようやく、隠していた邪悪な表情を彼女に見せつけた。
「いい子だ。そのまましばらく、おやすみ…」
俺の黒い手袋によって目を覆われたサキは、そのまま静かに眠った。
勝利を確信した俺は、運転席に乗り込み車を発進させた。
もちろんその車には、他に誰も乗ってなどいなかった。
・・・・・・
俺の宇宙船は、C9コロニーの外の荒地に停泊してある。
したがって、サキを宇宙船に連れて帰るにはコロニー外壁の検問ゲートを通らなくてはならない。
当然ながら、このまま検問ゲートを潜れば後部座席で眠っているサキの姿が記録されてしまい、俺は誘拐の容疑者としてお縄につくことになるだろう。
だからコロニー内部でターゲットを拉致した場合、外へ運び出す前に一手間作業を加える。
コロニーの外れの人通りがほぼないところで、俺はワゴン車を停めた。
後部座席で眠るサキのすぐ横には、荷物の運搬用コンテナが載せてあった。小型のコンテナだが、人一人が丸まって入れるぐらいの大きさだ。
このコンテナは赤外線やサーモグラフィーといった探知システムをごまかせる特殊構造になっていて、検問ゲートのシステム程度なら用意に中身を欺ける。
これから少しの間、サキにはこの中で大人しくしていてもらう。
ガチャリ! ガチャリ!
中で暴れられては困るので、手錠と足錠で四肢の自由を封じた。
中から音は漏れない設計だが、念のために防声マスクを装着する。
防声マスクは顔の鼻から下を覆い尽くすゴム性のマスクで、内面の口に当たる部分にはマウスピース状のパーツが付いている。それを噛ませた上でマスクを装着すれば、噛み締めた状態から口を開くことができない。マスクは鼻孔の部分に穴が空いており、呼吸はできるがきっと苦しいだろう。少しの間、彼女には辛抱してもらうことになる。
「ん、ぐ…」
ギュムム…パチッ!
マウスピースを噛ませ、ぴっちりと顔の下半分をマスクで覆った。
最後に彼女の位置情報がバレたりしないよう、ジャミング装置を起動してパーソナルデバイスの機能を封じる。
これで彼女の足取りはもう誰にもつかめない。
身体を折りたたんでコンテナの中に詰め込み、分厚い蓋をして他のコンテナに紛れ込ませる。
このワゴン車は荷物の運搬をしているだけのように見られ、人が誘拐されているとは思われないだろう。
全ての作業を終え、俺はワゴン車をコロニーのゲートに向けて走らせた。
ゲートが近づくたび、緊張度は増していった。
「大丈夫だ、何度もシミュレーションはしているからな」
生身の人間ではなく、動物をコンテナに詰めて検証した。
結果、一度もゲートの検問に引っ掛かっていない。
失敗などありえない。
背中にジワリと汗をかきながら、ワゴン車はゲートの前に到着する。
『ゆっくり前進してください』
規定の速度で少しずつ車を進め、様々なセンサーで検査を受ける。
もしもなにか異変を探知されたら、ブザーがなるはずだ。
心臓がバクバク鳴っていた。検査の時間は1分にも満たないのに、数十分にも感じられる。
『オールグリーンです。外出を許可します』
検査をパスしたことで、目の前のゲートが開いた。
俺はサキを連れて、C9コロニーの外へ脱出することに成功したのだ。
「くくく…ハハハハハ! やった! やったぞ!」
コロニー外の荒地を走る間、俺は車の中で歓喜の雄叫びを上げた。
長く夢見た拉致計画が、思い通りに運んだ。
美しい小娘を宇宙船の中に連れ込んで、好き放題できる。
そんな夢のような生活がついに実現するのだ。
宇宙船に向かうまでの道中、俺の運転はかなり荒れていたかもしれない…